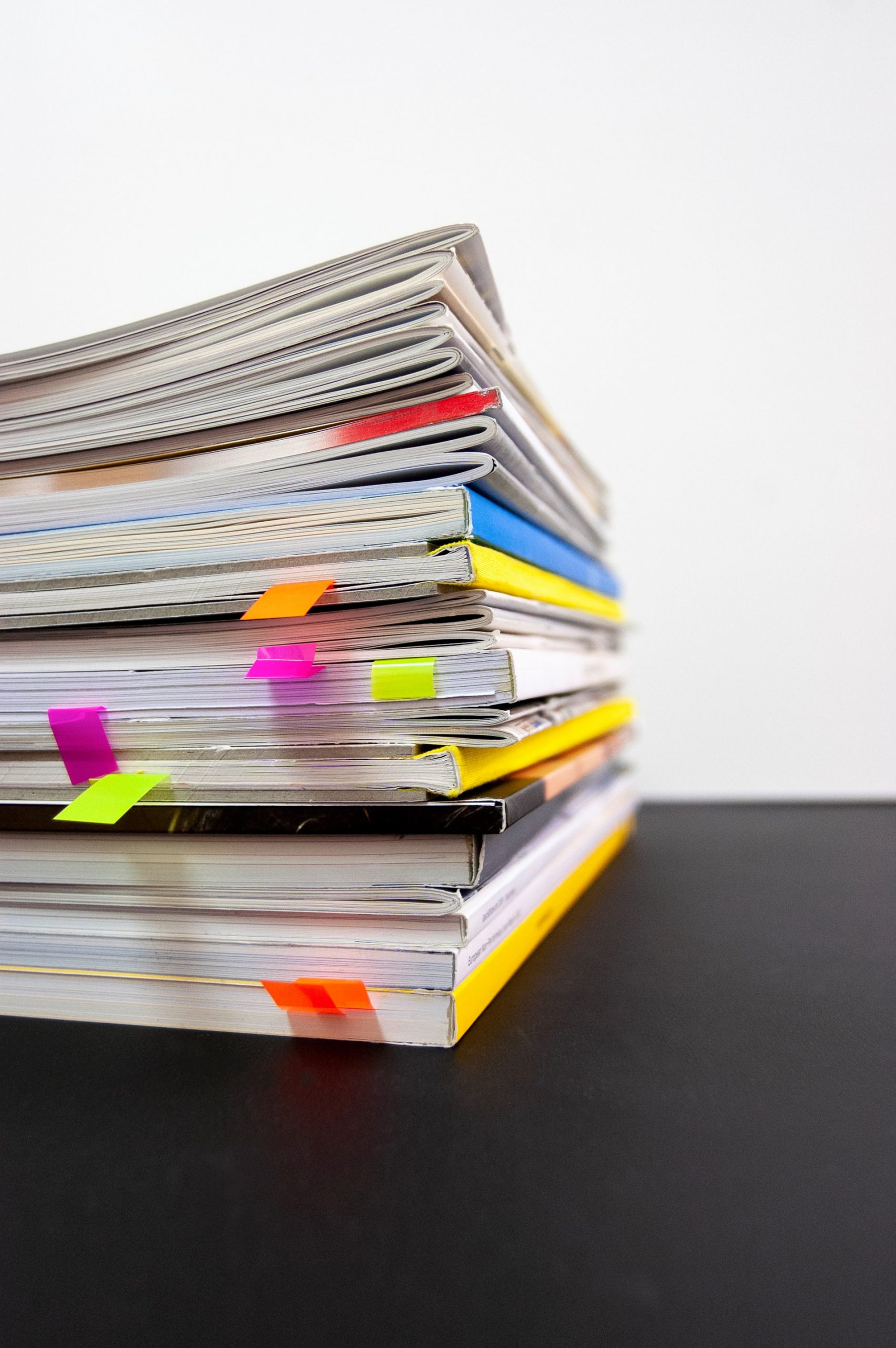雑貨屋を営んでいますが、雑貨の他にクッキーやティーバッグ、コーヒーなどの食料品を一部取り扱っています。消費税軽減税率が始まり、その中で気を付けるべきことは何かありますか?
1.店員さんが注意すべき点が2点あります。
①食料品とそれ以外の商品が一体として販売される一体資産については、税抜き価格が1万円以下で、かつ食品価格の割合が3分の2以上である場合に限り軽減税率の適用があること
②食料品の販売に際して使用される包装材料および容器については、食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用される場合に限り軽減税率の対象となること2.店内の表示について注意すべき点は、軽減税率の適用がある旨の表示を行うことが望ましいこと。例えば店内飲食と持ち帰りの場合の価格を分ける、食料品には軽減税率の適用がある旨の表示を店内で行うなどの方法があること。3.経理処理について注意すべき点は、仕入税額控除の適用を受ける場合に軽減税率の対象品目であることがわかる記載を要すること。例えば帳簿において総勘定元帳に軽減税率対象品目に記号を記載し、その記号が軽減税率対象品目であることを示すこと。4.決算の時の処理について注意すべき点は、税抜処理では特に必要ないことですが、税込処理では売り上げが税込で入ることから、売上につき軽減税率が含まれるか否かで区分が必要となります。5.その他に注意すべき点としては、軽減税率に別途手続きは必要ないことと、商品券を使った場合については、商品券を使った場合は非課税となるので、最低限帳簿にその旨の記載をすることなどです。
雑貨屋やカフェで商品を販売している方にとって、
消費税の軽減税率は、日々の会計や経理に関わる大切なルールです。
食品と雑貨が混ざった商品や、店内飲食と持ち帰りでの価格設定など、ちょっとしたポイントを押さえておくと、会計や帳簿付けがスムーズになります。
この記事では、軽減税率の基本ルールや
店員・経理担当者が気を付けることを、やさしい言葉で整理しています。
目次
1. 店員さんが気を付けるポイント
店員さんが特に注意したいのは、食品と雑貨が混ざった商品の扱いです。
軽減税率は食品にだけ適用されるので、どの商品が対象かを理解しておく必要があります。
- 食料品と雑貨がセットになった商品は、税抜価格1万円以下で食品の割合が2/3以上の場合に軽減税率が適用されます。
- 食品の包装や容器は、販売に必要なものとして使用される場合のみ軽減税率対象です。
販売時に迷わないよう、商品のラベルや表示で軽減税率の対象かどうかを確認できるようにしておくと安心です。
2. 店内表示の工夫
お客さまが商品を選ぶとき、軽減税率の対象かどうか分かるように表示することが大切です。表示を工夫すると、会計時のトラブルや混乱を防げます。
- 店内飲食と持ち帰りで価格を分けて表示する
- 食品には「軽減税率対象」とラベルやポップで示す
- レジ近くや棚に対象商品の説明を掲示する
このように目に見える工夫をしておくと、お客さまも店員も安心して販売・購入できます。
3. 経理処理の注意点
経理では、軽減税率対象の仕入れや売上を帳簿に分かるように記録することが重要です。
帳簿がわかりやすいと、税務処理も安心です。
- 総勘定元帳に軽減税率対象品目の記号を付けておく
- 仕入税額控除を受ける場合は、対象品目であることを明示する
- 会計ソフトを使う場合も、軽減税率対象として区分して入力する
こうすることで、申告の際に軽減税率の計算やチェックがスムーズになります。
4. 決算時の処理
決算のときは、売上や仕入れの金額に軽減税率が含まれているかどうかを確認して、区分して計算する必要があります。税抜処理の場合は大きな問題はありませんが、税込処理の場合は売上を軽減税率対象とそれ以外に分けて記録することがポイントです。
この区分をきちんとしておくと、決算書の作成や税務署の確認時にも混乱せず、安心して申告できます。
5. その他の注意点
最後に、軽減税率に関するその他の注意点をまとめます。日常の販売や帳簿管理に役立つポイントです。
- 軽減税率のための特別な手続きは不要です
- 商品券を使った場合は非課税になるので、帳簿にその旨を記録しておく
- 対象商品の表示や帳簿記録を最低限整えておくと安心
軽減税率は最初は少し複雑に感じますが、
表示・帳簿・区分のルールを守るだけで、販売や決算もスムーズになります。